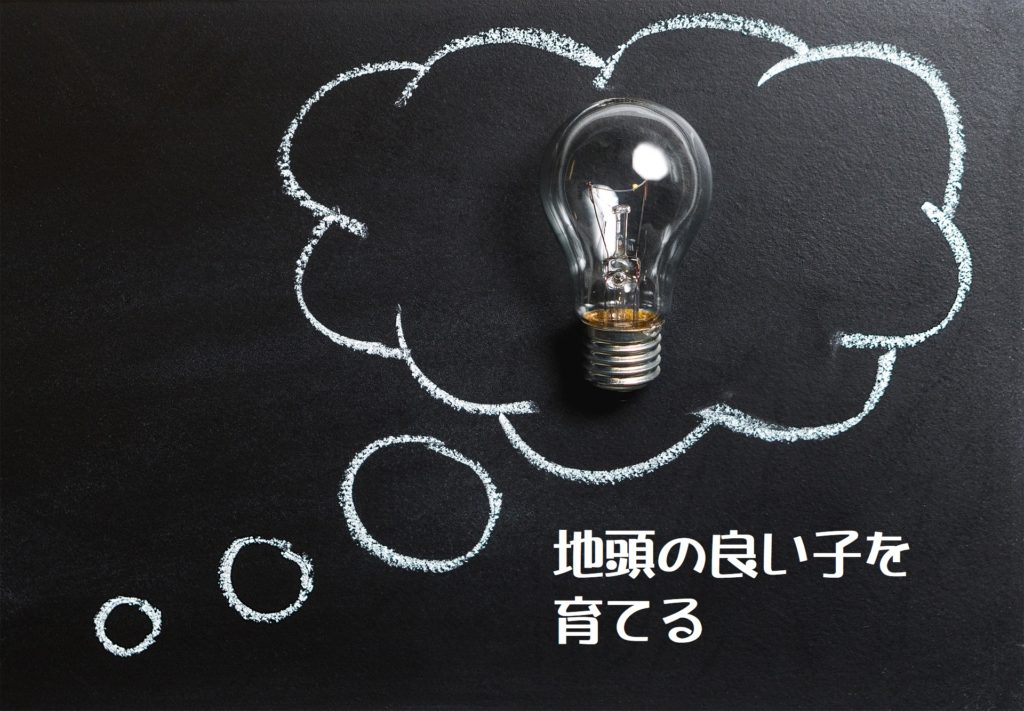 どんな親御さんでも、ご自身のお子さんに頭が良くなって欲しいと願うものです。ただ、「頭の良い子」というのはどういうこどものことをいうのでしょうか。
どんな親御さんでも、ご自身のお子さんに頭が良くなって欲しいと願うものです。ただ、「頭の良い子」というのはどういうこどものことをいうのでしょうか。
頭の良い子 = 成績の良い子、という関係は成り立つと思います。頭が良い子は、おそらく成績は良いのでしょうが、では逆に成績が良い子は、頭が良い子と言えるのでしょうか。
「地頭の良さ」という表現が何年か前から使われるようになりましたが、「頭の良い子」と「地頭の良い子」とはそもそも何かが違うのでしょうか。
そして「地頭の良さ」とは生まれ持つ遺伝的な要素によるものなのでしょうか。それとも育て方で養える能力なのでしょうか。
今回はそのあたりに焦点をあてていきたいと思います。
目次
地頭を良くできるのか
まず、こどもに良い教育環境を整えて、学力をつけさせるということは、そもそもどういった目的(動機)に基づいて行われるのでしょうか。
「まわりの親がみんなやっているから」とか、「塾に行かせないと何か取り残された感じがする」や、あるいは「なんとなく学力を向上させるほうが良いと思うから」でしょうか。はたまた、その先にある「良い大学に入学させること」でしょうか。更にその先の「良い仕事につかせるため」でしょうか?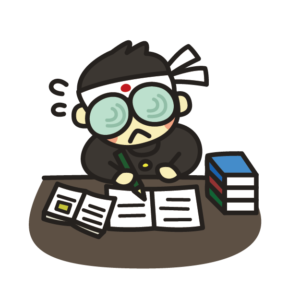
もちろん、上記いずれの内容も、こどもの教育に力を注ぐ妥当な動機になるとは思います。
ただ、それらが本当にこどもの将来のために必要な条件なのでしょうか。
一生懸命努力をして、たくさん知識を身につけたり、算数、数学などの難しい解法を覚えることはそれはそれで必要だと思います。
ただ、よい成績をとることのみに目が行ってしまう教育には問題があると思います。
そもそも、こどもがどの様に成長して欲しいかということについて、みなさんはどの様にお考えでしょうか。ご家庭ごとに様々で、「好きなことをやってのびのびと育って欲しい」、「良い成績をとって将来は安定した生活を送って欲しい」、「人のためになるような大人になって欲しい」など、多様な価値観があると思います。
受験などの難関を乗り越えること以外に、こどもが自立し、良い人生を送る為には、どの様な能力を身につけさせれば良いでしょうか。もちろん勉強ができるに越したことはありませんが、それだけではなく「生きるための力」をつけてあげなくてはなりません。
現代のような変化の大きな時代において、「臨機応変に対応できる力」、それが今後は必要になります。
それらは、「ちょっとした変化を感じ取る洞察力」であったり、他の人たちの協力を得るための「コミュニケーション能力」であったり、「俯瞰的に物事をみて判断する力」、などになります。
こういった能力を持つ人が、世の中では「地頭が良い人」と言われています。
このような能力は、生まれつきのものなのでしょうか。それとも教育によって得られるものなのでしょうか。
地頭の鍛え方
結論から言うと、地頭を良くする(鍛える)ことは可能です。
地頭を良くするということは「自ら考える能力をつけさせること」に他なりません。困難にぶち当たった時に、状況を的確に判断し、周りの協力をとりつけ、決断を行える能力、それらを養う必要があります。
 そのためには、こどもに幼少期からある癖をつけさせる必要があります。
そのためには、こどもに幼少期からある癖をつけさせる必要があります。
「なぜそれが必要なのか」、「なぜそうなるのか」、「なぜそれは間違いなのか」など、幼少のころから自ら考えるようにさせなければなりません。こどもの疑問に対し、親などの周りの人間がすぐに回答を与えてしまわないことが重要です。
そのためには、こどもには様々な体験をさせましょう。こどもが興味をもつことには出来るだけ体験できるように環境を整えてあげましょう。そして興味をもつ本は何でもたくさん読ませましょう。多様な体験や読書を通じて色々な考え方や、判断力が養えるようになります。
また、それらの体験を通して発生する疑問については、親子で一緒に考えることが肝要です。親が答えを教えるのではなく、一緒に考えてあげる、こどもが自発的に答えを探すように仕向ける、これが重要です。
問題集を解くような、答えのある問題にとりくむことも当然必要ですが、自分から考える力を養うことはそれ以上に必要不可欠な能力ですので、常日頃から気をつけて取り組んで頂きたいと思います。
今回のまとめ
いかがでしょうか。今回は、「地頭の良い子」を育てるためには、親の側にどのような考え方が必要かということについて書きました。要点を以下にまとめます。
- 「地頭が良い」とは、「変化を感じる洞察力」があり、他人の協力を得る「コミュニケーション力」であったり、「俯瞰的に物事をみて判断する力」といった能力のことと考えられる。
- それらの能力は「自立して良く生きるために必要な力」に他ならない。
- こどもの教育で最も大切なことは、「生きるための力」を身につけさせることにある。
- 上記から、こどもの地頭を良くすることが、教育するうえで肝要であることがわかる。
- 地頭を鍛えるためには、常日頃から自ら考える癖をつけさせる必要がある。
- そのためには、いろいろな体験をさせ、様々な問題に対し主体的に解決するよう教育する必要がある。
ご参考になさってください。
参考文献
日系DUAL:http://dual.nikkei.co.jp/atcl/column/17/102300014/102600012/
転職クエスト:http://design-career.com/jiatama1
子どもが聴いてくれる話し方と子どもが話してくれる聴き方 大全:https://www.amazon.co.jp/
コメントを残す