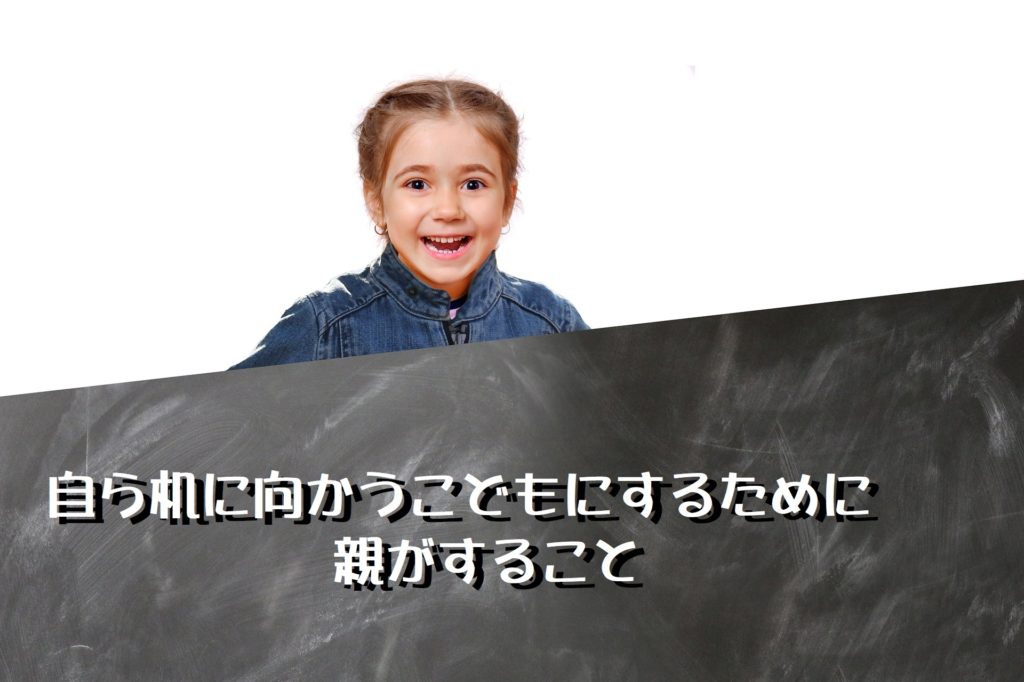
皆さんのお子さんは、勉強をするために自ら進んで机に向かうでしょうか。
大抵はそのようなことはなく、親が口酸っぱく「宿題やったの?」や、「ゲームばっかりやらないで勉強しなさい!」と促して、ようやく渋々勉強机に向かう、という状況だと思います。
「こどもが自ら机に向かって学習する」、というのは親がこどもに抱く理想の姿だと思いますが、このように主体的に行動できるこどもは希にしかいない思います。
ただ、いわゆる超難関大に合格した学生へのインタビューでは、ほとんどが自身の小学生だった頃を含めたこども時代には、親に勉強をしろと言われたことがない、と回答するという話をよく聞きます。
これは、こどもの資質によるのでしょうか。
それとも家庭の環境や親の対応による結果なのでしょうか。
今回はそのあたりに焦点をあてていきたいと思います。
目次
こどもは注意力散漫
高校生くらいであれば、自分の意志で机に向かって勉強をすることはあるでしょうが、基本的に、小学校低学年のこどもは自ら机に向かって主体的に勉強をするということはありません。
 こどもは机に向かってじっとするといったことはできません。常に色々なことに注意が発散し、ウロウロ行動してしまうのがこどもの特性であり、自然な姿です。
こどもは机に向かってじっとするといったことはできません。常に色々なことに注意が発散し、ウロウロ行動してしまうのがこどもの特性であり、自然な姿です。
親がこどもの中学受験等を意識し始めて、我が子の為と思っていきなり「今日から毎日漢字と計算のプリントをやるぞ!」と意気込んだとしても、恐らくこどもにはその熱い思いは伝わらず、空振りに終わることが多いと思います。
こういった親の気持ちをどのようにこどもの行動へと結び付けていけばよいのでしょうか。
こどもに自ら行動を促すような方法はあるのでしょうか。
中学受験の準備は、小学校4年生頃から始めるということが多いと思います。その頃までに、出来るだけ自分で勉強に向き合えるような状態になっているのが望ましいですが、どのように動機付けすればよいでしょう。
興味があることをさせる
まず、どんな短時間でも良いので、学習することを習慣づけさせる、ということが大事です。
ただ、こどもは楽しくないことには興味を示しませんし、それを無理やりやらせようとしても逆効果となるだけです。
まずは、こどもが興味を示すことであれば何でも良いので、それについてわからないことがあれば調べるようにうまく仕向けたり、また何か好きなことを更に上手にするには、何をどのようにすれば良いかを考えさせて、紙に書いてまとめさせる、といったところから始めるのが良いでしょう。
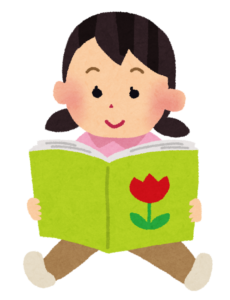 こどもは興味があることについては、一生懸命知ろうとしますし、自分でやってみたいことがあれば、上手に出来るようになろうと頑張ります。
こどもは興味があることについては、一生懸命知ろうとしますし、自分でやってみたいことがあれば、上手に出来るようになろうと頑張ります。
楽しいこと(遊び)の延長として、学習の習慣づけをさせるとよいでしょう。
例えば絵が好きなこどもであれば、描いたものを本や図鑑で調べるようにさせることで、更に知ろうとする探求心を養うことができますし、お菓子が好きなこどもであれば、何で出来ていてどこで造られているかなどを親と一緒に調べることで、材料や場所などの付随する情報を吸収できるようになるでしょう。
受験に必要な勉強につい目が行ってしまいがちですが、まずはこどもが好きなことを伸ばしてあげるという心構えで臨むとよいでしょう。
学ぶことを習慣づけさせるには、とっかかりは何でもよいと思います。「こどもが興味のあること」がキーワードです。
ある程度日々の習慣づけが出来た後には、親はその他にどのようなフォローが必要でしょうか。
まず、学習する場所ですが、こどもが小さいうちはリビングルーム等、誰か家族の目が届くところでさせるようにしましょう。
また、毎日同じ時間に学習するようにすることも大事です。親が何も言わなくても決まった時間に学習が始められるように習慣づけることが必要です。
今回のまとめ
いかがでしょうか。こどもが自ら机に向かい学習する習慣をつけさせることは、なかなか難しく度のご家庭でもお悩みの点だと思います。今回は、こどもが小学校低学年の幼い頃からそのような習慣がつくような動機付け方法について書きました。要点を以下にまとめます。
- こどもは基本的には、自分から机の前に座って勉強に取り組むといったことはしない。
- こどもは小学校低学年の頃は特に、興味のないことに集中するということは出来ないということを理解する。
- まずは短時間でも良いので、こどもが興味を示す内容について、わからないことを探求する癖をつけさせ、知識を深堀りさせる。
- こどもは楽しいことには集中できるため、遊びの延長として学習習慣をみにつけさせる。
- 家族が目の届く範囲でこどもに学習させる。
ご参考になさってください。
参考文献
ベネッセ教育情報サイト:http://benesse.jp/kyouiku/200812/20081218-5c.html
President ONLINE:http://president.jp/articles/-/22547?page=1
SankeiBiz:https://www.sankeibiz.jp/econome/news/170917/ecd1709171307003-n1.htm
コメントを残す